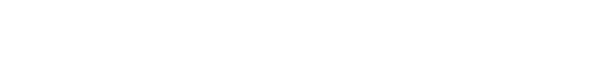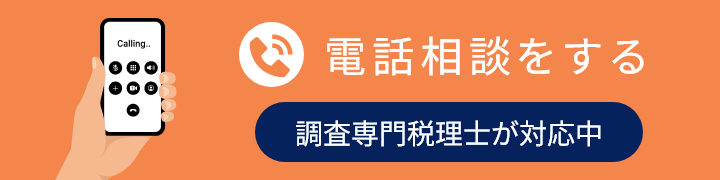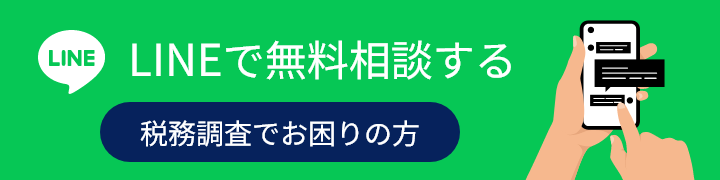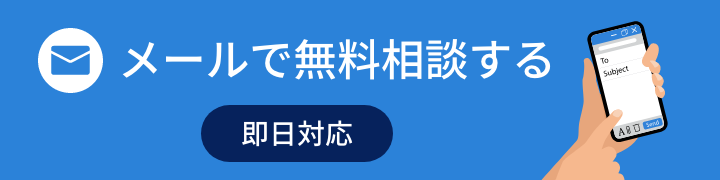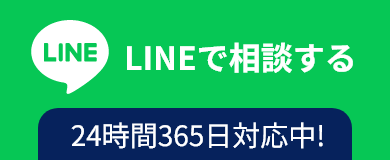目次
税務調査が一度終わったにもかかわらず、ある日突然「再調査」が通知されることがあります。これは珍しいことではあるものの、実際に発生するケースも存在します。例えば、取引先に対する調査から新たな情報が得られた場合や、過去に見逃されていた資料が発見されたケースなどです。
この記事では、再調査が行われる具体的な事例や理由と、再調査での対応方法を分かりやすくご紹介します。事前に知識を持っておくことで、万が一の際も冷静に対応できるようになるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。
税務調査の再調査とは?
税務調査が一度終わったにもかかわらず、同じ課税期間や税目について再び税務署が調査を行うことがあります。これがいわゆる「再調査」です。再調査には一定の条件があり、原則として無条件に実施されるものではありません。
ここでは、再調査の仕組みについてわかりやすく解説します。
再調査は実地調査に対して行われる
再調査は、電話や書面でのやりとりではなく、税務署の職員が直接企業や個人事業主の元を訪れて帳簿などを確認する「実地調査」に対して行われるものです。これは、税務調査の中でも一般的な形式で、すでに一度実地調査が終わっているにもかかわらず、同じ税目・同じ期間に対してもう一度行われるのが「再調査」です。
たとえば、ある年の「所得税」「法人税」「消費税」などについて、すでに調査が行われていたとしても、同じ年・同じ税目を対象に再度調査されるケースが該当します。
税務署が再調査を行う根拠となる法的規定
税務署が再調査を行う根拠は、国税通則法第74条の11第5項にあります。この法律では、「新たに得られた情報に照らして非違(法律に違反していること)があると認められる場合」に限り、再び質問検査権(調査する権限)を使って調査できると定められています。
つまり、「念のためもう一度調べたい」といった理由では再調査は行えず、新たな事実や証拠の発見が必要になります。さらに、再調査を進めるには、国税庁内の通達に基づいた厳格な判断手続きも求められます。
このように、税務署側も慎重に再調査の必要性を判断しており、めったに行われるものではありませんが、可能性がまったくないわけではない点には注意が必要です。
税務調査後に再調査となる主な4つの理由
一度税務調査が終わったにもかかわらず、再び調査が行われるのが「再調査」です。これはごくまれなケースではありますが、「非違の可能性がある新たな情報」が見つかった場合など、一定の条件を満たせば実施されることがあります。
この記事では、再調査が行われる主な4つの理由を実際の事例を交えてわかりやすく解説します。事前に理由を把握しておけば、万が一通知が届いた場合でも冷静に対処することができるでしょう。
取引先の税務調査から新たな情報が得られた場合
再調査の典型例として多いのが、取引先の税務調査を通じて新たな事実が判明するケースです。税務署は「反面調査」と呼ばれる手法を用い、取引先から提出された帳簿や資料をもとに、関連企業の取引内容を照合・検証することがあります。
例えば、取引先の帳簿に記載された仕入金額と、自社が計上している売上金額に食い違いがあった場合、それが「非違」の兆候と見なされる可能性があります。
※「非違(ひい)」とは、税法に違反する行為や申告の誤りが疑われる状態を指します。意図的な不正だけでなく、認識不足による記載ミスや計上漏れも含まれるため注意が必要です。
このような非違の可能性が生じた場合、税務署は新たな事実に基づいて再調査を行うことがあります。
過去の調査対象外期間に非違が見つかった場合
税務調査は通常、数年分の申告内容に限って行われます。しかし、調査の対象外だった年度についても、後から新たな情報が見つかれば、再調査の対象になることがあります。
たとえば、直近の年度で大きな申告漏れが見つかり、その内容が過去の申告とつじつまが合わない場合、税務署は「過去の年度にも非違があった」と判断し、再調査に踏み切ることがあります。つまり、現在のミスがきっかけで、過去の問題が掘り起こされることもあるのです。このように、過去に見逃された問題が現在の情報から発覚することもあるため、定期的に過去の申告を見直しておくことも再調査の対策に繋がります。
法定調書や資料せんなどから非違が推認される場合
税務署は、調査対象になっていない期間でも、さまざまな情報をもとに申告内容を確認しています。たとえば、「法定調書」「支払調書」「資料せん」などに記載された情報と申告内容に食い違いがあると、非違があったと判断されることがあります。
また、取引記録や匿名の通報など、第三者から得られた情報が、証拠として裏づけられた場合も要注意です。本人に悪意がなかった場合でも、帳簿や資料の管理が不十分だと「不適切な申告」と見なされる可能性があります。日頃から正確な記帳や書類の保管を徹底することが重要です。
第三者からの情報提供や密告があった場合
元社員や取引先など、社内外の関係者からの情報提供(いわゆる密告)も、再調査のきっかけになることがあります。とくに内部の事情に詳しい人物からの通報は信頼性が高く、税務署が事実確認のために再調査を検討する材料となります。
密告があったからといってすぐに再調査が行われるわけではありませんが、その内容に裏付けとなる証拠や他の情報との整合性があれば、調査の再開が正当化される場合があります。関係者とのトラブルを避ける意味でも、普段から経理処理の透明性と説明責任を意識することが大切です。
再調査になるリスクはどれくらいある?
税務調査が問題なく終わったからといって、「再調査」の可能性が完全になくなるわけではありません。ただし、再調査は通常の調査と比べて実施される頻度が低く、実際に行われるのはごく一部の特殊なケースに限られます。
この記事では、再調査が行われる背景やそのリスクについて、知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。
一般的な企業や個人事業主における再調査の発生頻度
税務署が一度終了した調査を再度行うケースは、非常にまれです。再調査が実施されるには、「新たな情報が得られたこと」そして「非違の可能性があること」という2つの条件が必要になります。
そのため、日ごろから正しい申告と帳簿管理を行っている企業・個人事業主であれば、再調査のリスクはきわめて低いといえます。ただし、外部の状況が影響して再調査が行われるケースもあるため、常に一定の注意は必要です。
是認通知が出ていても再調査の対象になることがある
税務調査の結果、「是認通知(問題なしの通知)」が発行されることがあります。これは、調査時点で申告内容に問題がないと認められたことを意味します。
しかし、是認通知が出ていても後日新たな情報や証拠が税務署に届いた場合には、再調査の対象となることがあります。たとえば、調査後に取引先の不正が発覚し、その関係書類から過去の取引に疑いが生じたようなケースが該当します。
是認通知は「その時点での判断」に過ぎないため、結果に安心しきるのではなく、引き続き適正な経理処理を続けることが大切です。
もし再調査の通知が来たらどうすべき?
税務署から再調査の通知が届いた場合、驚きや不安を感じるのは当然ですが、慌てて対応を誤ると、状況が悪化するおそれもあります。再調査はあくまで「新たな情報に基づく非違の疑い」があって行われるものであり、適切な対応によって大きなトラブルを避けることも可能です。
ここでは、再調査の通知が届いた際にとるべき行動を3つのポイントで解説します。冷静に対応するためにも、事前に対応方法を把握しておくと安心です。
放置せず早めに税理士へ相談する
再調査の通知を受けた場合、最も重要なのは速やかに専門家である税理士に相談することです。自社だけで対応しようとすると、必要な資料の不備や説明の不正確さによって、かえって状況を悪化させてしまう可能性があります。
特に再調査は、税務署側がすでに何らかの疑念を抱いている状況で行われるため、些細な受け答えが調査官の心証に大きな影響を与えることもあります。こうしたリスクを避けるためにも、税務調査対応に豊富な実績を持つ専門家にサポートを依頼するのが安心です。
税理士法人GNsでは、税務調査に関する専門サービスを提供しており、実地調査への立ち会いや指摘事項への対応、修正申告の判断支援などをトータルでサポートしています。再調査のようなプレッシャーの大きい局面こそ、経験豊富な税理士に早めに相談することがスムーズな解決への第一歩となります。
求められた書類は迅速かつ正確に提出する
再調査では、税務署から帳簿や証憑資料の提出を求められることが一般的です。ここで求められる書類を迅速かつ正確に整えて提出することが信頼構築につながります。もし書類が散逸していたり記録が曖昧であったりすると、税務署側に「隠ぺいの意図があるのではないか」と疑われかねません。
また、提出に遅れが生じることで調査が長期化するおそれもあります。日頃から資料の保管と整理を徹底しておくことが、いざという時の対応力を高めることにつながります。
修正申告と更正処分の違いを理解しておく
調査の結果、申告内容に誤りがあった場合には「修正申告」または「更正処分」が求められる可能性があります。修正申告は納税者の自主的な修正であるのに対し、更正処分は税務署が一方的に課税内容を訂正するものです。
修正申告を行うと加算税が軽減される場合もあり、状況によっては自発的に対応する方が良い場合もあります。どちらの手続きを選ぶかはケースバイケースですが、税理士と相談しながら冷静に判断を下すことが重要です。制度を正しく理解しておくことで、無用なトラブルや余計なコストを避けることができます。
税務調査の再調査についてよくある質問
税務調査の「再調査」については、実際に通知を受けたときだけでなく、将来に備えて不安を感じている経営者からも多くの相談が寄せられます。
ここでは、中小企業の経営者や個人事業主が特に気にする疑問を取り上げ、具体的かつ実務的な視点でお答えします。
税務調査後どれくらいの期間で再調査が行われる?
再調査に具体的な時期の決まりはありませんが、一般的には前回の調査から数ヶ月〜1年程度の間に通知されるケースが多いとされています。これは、税務署が取引先の調査や法定調書の確認などを経て、新たな情報を得るまでにある程度の時間がかかるためです。
また、外国税務当局との情報交換を経て再調査となるケースでは、数年後に突然通知が来ることもあります。そのため、調査が終わっても申告書や証憑資料の保管は最低7年間は続けるべきです。
再調査でペナルティになる場合はある?
再調査の結果、非違が確認された場合には、過少申告加算税や重加算税などのペナルティが課されます。特に、意図的な申告漏れや不正経理が認定された場合は重加算税の対象となり、税額の35%〜40%が追加で課税される可能性があります。
また、追徴課税に加えて延滞税が加わります。こうしたペナルティを防ぐには、再調査前の段階で税理士に相談し、疑わしい点について必要に応じて自主的に修正申告することもおすすめします。
まとめ
税務調査が一度終わったからといって必ずしも安心できるわけではありません。新たな情報に基づいて非違の可能性があると認められた場合、税務署は同じ年度に対して再調査を行うことが法的に認められています。特に、取引先の調査結果や第三者からの密告、法定調書などがきっかけで再調査に発展することがあるため、日常の税務処理においても慎重な対応が求められます。
万が一再調査が実施された場合でも、慌てず冷静に対応することが大切です。その際には税理士に相談しながら、必要な書類の準備や調査官への説明に備えることで、過度な追徴課税やトラブルを防ぐことが可能になります。こうした場面に備えて、ふだんから正確な記帳や証憑書類の保管、税制に関する基本的な知識を身につけておくことが重要です。
再調査に不安を感じている方や、事前にしっかりと備えておきたい方は、税務調査に強い税理士法人GNsへの相談をおすすめします。税理士法人GNsでは、調査の立ち会いから是正の提案、税務署との交渉まで一貫して対応しており、安心して任せられる体制が整っています。一人で抱え込まず、経験豊富な税理士法人GNsと一緒に乗り越えていきましょう。