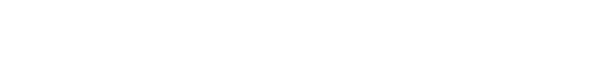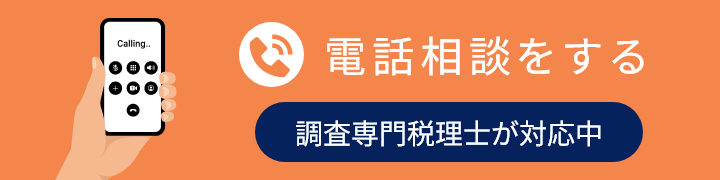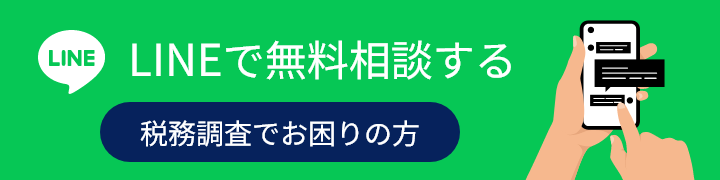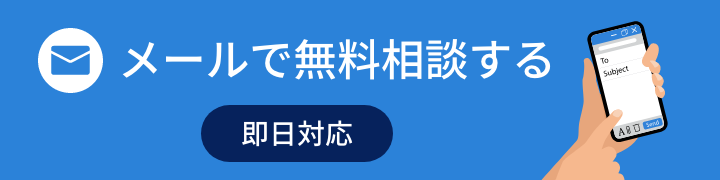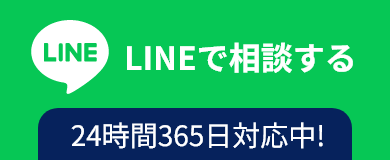目次
税務調査によって申告漏れや納税不足が発覚すると、本税(不足分)に加えて加算税と延滞税が課されることになります。これらの税金は、申告内容に誤りがあったこと、期限内に申告しなかったことや税金を納期限内に納めなかったことに対するペナルティとして位置づけられています。
追徴課税の一環として課される加算税や延滞税に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。「一体いくら請求されるのか」「どのように計算されるのか」「軽減できる方法はあるのか」といった疑問を持つのは当然です。
この記事では、加算税と延滞税の違いから種類・計算方法・軽減措置・試算例・相談のタイミングまでを詳しく解説します。正しい知識を持つことで、不要な支出やリスクを回避でき、安心して対応ができるようになります。
加算税の種類と特徴を理解しよう
加算税は、申告内容に誤りがあったり、そもそも申告をしていなかった場合に課される「罰則的な税金」で、不足税額に対して一定の税率で計算されます。延滞税が納付の遅れに対するペナルティなのに対して、加算税は申告の不備や悪質性に応じて課されます。
ここでは、代表的な3つの加算税とその違いについて解説します。
過少申告加算税が課されるケース
過少申告加算税は、すでに確定申告をしていたが、税務調査などによって不足税額が見つかった場合に課される加算税です。
対象となる例
- 売上の一部を申告漏れしていた
- 経費を過大に計上していた
- 所得の一部を除外していた
- 申告書の記載や税額計算を誤っていた
税率は以下のように定められており、税務調査の前後で変動します。
| 状況 | 税率 |
| 調査通知前の自主修正申告 | 0% |
| 調査通知後(更正予知前) | 5% (50万円超部分10%*) |
| 調査後(更正予知後) | 10% (50万円超部分15%*) |
*増差税額のうち、当初申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超えている部分に対してはかっこ書きの高い税率が適用されます。
税務調査が通知された後では、加算税が確実に課されるため、申告内容に誤りがあり納税が不足していることが分かっている場合は調査が通知される前に、自主的に修正申告を行うのが得策です。
無申告加算税が課されるケース
無申告加算税は、申告義務があるにもかかわらず、申告期限までに申告をしていなかった場合に課される加算税です。納税義務があるのに申告していないことは、税務署から特に問題視されます。
対象となる例
- 所得税や法人税の申告を失念していた
- インボイス登録をしたにもかかわらず、消費税申告をしていなかった
- 「どうせバレない」と考えて無申告だった(副業収入など)
税率は以下の通りです。
| 状況 | 税率 |
| 自主期限後申告 | 5% |
| 調査通知後 | 10% (50万円超300万円まで15%) (300万円超25%) |
| 調査後 | 15% (50万円超300万円まで20%) (300万円超30%) |
申告義務を果たしていない場合は、延滞税に加えてこの無申告加算税が重くのしかかるため、早めの対応が必要です。
重加算税が課されるケース
重加算税は、意図的な不正や仮装・隠蔽行為があった場合に課される、最も重いペナルティ税です。
該当する行為の例
- 意図的な売上除外や二重帳簿の作成
- 架空経費の計上
- 帳簿書類などの改ざん・捏造
- 他人名義の口座を使って所得を隠す
重加算税の税率は、他の加算税よりも高く設定されています。
| 内容 | 税率 |
| 過少申告に重加算税が課された場合 | 35% (5年以内に前歴がある場合などは45%) |
| 無申告に重加算税が課された場合 | 40% (5年以内に前歴がある場合などは50%) |
悪質性が高いと判断された場合は、重加算税に加えて刑事告発や調査の頻度増加といった影響も受けかねません。
延滞税の仕組みと計算方法を徹底解説

延滞税とは、税金の納付が期限を過ぎた場合に発生する「利息のような税金」です。たとえ少額でも、納期限を1日でも過ぎていれば発生するため、納税のタイミングには注意が必要です。
特徴とポイント
- 原則として納期限の翌日から発生
- 本税(追加で納めるべき税金)に対して年利で課される
- 毎日計算される(日割り計算)
- 修正申告や更正があっても、その起算日は変わらない
延滞税は税率が年によって異なり、納付が遅れるほど金額が大きくなります。また、税務調査をきっかけに過去の申告ミスが見つかった場合には、数年前の税金に対して延滞税がつくこともあります。
ここでは、延滞税の基本的な計算方法と、発生条件、免除される可能性について詳しく解説します。
延滞税の税率と計算の基本式
延滞税は、延滞税率をもとに日割りで計算されます。税率は年度や期間によって異なりますが、基本的な計算式は共通です。
計算式の概要
延滞税額 = 本税 × 延滞税率 × 延滞日数 ÷ 365
延滞税率(令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間)
- 納期限の翌日から2ヶ月以内:年2.4%
- 納期限の翌日から2ヶ月経過後:年8.7%
例えば、100万円の税金が30日遅れた場合の延滞税は次のようになります。
100万円 × 2.4% × 30 ÷ 365 = 約1,900円(100円未満切捨て)
このように、短期間でも発生するため、できるだけ早く納付することが延滞税の負担を軽くするポイントです。
申告期限や修正申告による延滞税の違い
延滞税の発生は、納期限を基準に判断されます。つまり、修正申告で本税を追加した場合、その本税については元の納期限からの延滞とみなされます。
ポイントとなるケース
- 通常の確定申告で納付が遅れた → 延滞税が即発生
- 税務調査で修正申告 → 申告期限時点からの延滞扱い
- 還付申告の場合は延滞税が発生しない
修正申告の場合、過去の納期限にさかのぼって延滞税が計算されるため、数年分の延滞税がまとめて課されるケースもあります。
延滞税がかからない特例や免除の条件
すべてのケースで延滞税が課されるわけではなく、一定の条件下では免除される可能性もあります。特例を把握しておくことで、不要な支払いを避けられることがあります。
代表的な免除条件
- 災害・病気などやむを得ない事情があった
- 税務署長が延滞税の軽減を認めた場合
- 所得税や法人税の納付期限延長が正式に認められた場合
- 当初申告書を提出してから1年経過後に修正申告書を提出して追加納税額が発生した場合、当初申告から1年経過後~修正申告書の提出日までの期間(除算期間)は延滞税が発生しない(重加算税が課される場合を除く)
免除の可否は個別判断となるため、税務署に相談したり、税理士を通して確認するのが確実です。
加算税と延滞税を試算する具体例
加算税や延滞税は、理論的な説明だけでは実感が湧きにくいため、実際の金額イメージを把握することが大切です。ここでは、納税の遅れや税務調査後の修正申告により、どれくらいの加算税・延滞税が発生するのかを、具体的なシミュレーションを通じて解説します。
納税が遅れた場合の延滞税シミュレーション
前提条件
- 法人税(所得税)の本税:80万円
- 納期限からの延滞日数:90日
- 延滞税率:納期限の翌月から2ヶ月以内2.4%、それ以降8.7%
計算ステップ
- 納期限から2ヶ月(60日)
80万円 × 2.4% × 60 ÷ 365 = 約3,150円(1円未満切捨て) - 残り30日間
80万円 × 8.7% × 30 ÷ 365 = 約5,720円(1円未満切捨て)
合計延滞税:約8,870円→8,800円(100円未満切捨て)
延滞が長引くと利率が跳ね上がるため、納税の遅れは極力避けることが望ましいです。
調査後に過少申告を修正した場合の追加納付額試算例
前提条件
- 修正申告による本税:50万円(3年前の分)
- 追加納税額は修正申告と同時に納付
- 過少申告加算税:10%
- 延滞税:2.4% 1年分(1年経過後~修正申告日までは免除)
計算ステップ
- 加算税:50万円 × 10% = 50,000円
- 延滞税:50万円 × 2.4% × = 12,000円
合計追加納税額=本税+過少申告加算税+延滞税:562,000円
本税の50万円に対して、加算税と延滞税だけで62,000円が追加で発生します。
このように、過去の申告に対する修正は時間が経つほど負担が大きくなります。
延滞税や加算税を減額するための対策

加算税や延滞税は、税務調査を受けてから対応すると重い負担になりますが、調査前や指摘前に自主的に行動することで軽減や回避が可能なケースもあります。ここでは、ペナルティを抑えるために実践できる3つの具体的な対策を紹介します。
自主的に修正申告を行うメリット
税務調査前に、自ら誤りに気付き修正申告を行えば、加算税の軽減や延滞税の抑制につながることがあります。これは、国税庁が「自主的な納税行動」を促しているためです。
主なメリット
- 過少申告加算税や無申告加算税が軽減される
- 重加算税の対象となる可能性を低下させられる(調査の立会い前に修正した部分は原則重加算税の対象外)
- 延滞税が早く止まり、日数分の負担が減る
できるだけ早期に誤りを認識し、税務署に申告・納付することが、金銭面でも信用面でも大きなプラスとなります。
税務調査前に対応すべきチェックポイント
調査の連絡が来てから慌てて対応するのではなく、日頃から不備のチェックや記帳の見直しを行っておくことで、ペナルティのリスクを回避できます。
定期的に見直すべき項目
- 売上や経費の記帳と実態が一致しているか
- 領収書・請求書などの証憑が揃っているか
- 現金取引の記録が漏れていないか
- 過去の申告内容と現在の帳簿が整合しているか
少しでも心当たりのある箇所があれば、調査前の段階で修正申告を検討することが重要です。
税理士に相談することで得られる安心
不安があるまま放置してしまうと、加算税や延滞税が高額になるだけでなく、将来的に税務調査で高額な追徴税額を支払うリスクもあります。専門家である税理士に早めに相談することで、必要な対応や判断をスムーズに進めることができます。
税務調査に特化した支援を行う税理士法人GNsでは
- 修正申告や追徴課税に関する判断と実務サポート
- 加算税・延滞税を減らすための適切な申告タイミングの提案
- 税務調査時の同席・代理交渉なども可能
- 企業ごとの状況に合わせた税務リスク対策の立案
加算税や延滞税に関する対応は、正しい知識と経験のある専門家に任せることで精神的にも大きな安心が得られます。
加算税・延滞税に関するよくある疑問
加算税や延滞税に関する仕組みは複雑で、不安や疑問を抱える方も少なくありません。ここでは、納税者からよく寄せられる代表的な質問について、分かりやすく解説します。
加算税や延滞税は分割で納付できるのか
原則として、加算税・延滞税を含む税金は一括での納付が求められます。しかし、経済的な事情などにより納付が困難な場合、税務署に申し出ることで「納税の猶予」や「分割納付」が認められることがあります。
分割納付のポイント
- 税務署や市区町村へ事前に相談・申請が必要
- 納付計画書の提出を求められる
- 財産や収入状況の確認を受ける場合あり
- 原則として延滞税は納付猶予中も発生する
やむを得ない事情がある場合は、早めに税務署や市区町村へ相談することで柔軟な対応を受けられる可能性があります。
支払わない場合に起こり得る差し押さえリスク
加算税や延滞税を含む税金を滞納し続けると、最終的には財産の差し押さえや強制徴収の対象になる可能性があります。とくに悪質と判断される場合、猶予措置なしに一気に執行されることもあります。
差し押さえの対象となる財産
- 預貯金
- 給与や報酬(一定額を超える部分)
- 不動産・車両
- 売掛金・貸付金
こうした強制措置に至る前に、自主的な納付や分割納付の申請を行うことが非常に重要です。
追徴課税の時効はいつなのか
税務署が追徴課税を課す権利(課税権)には、一定の時効があります。しかし、条件によっては時効の中断や延長もあるため、注意が必要です。
基本的な時効期間
| 税目 | 時効期間 |
| 通常の申告漏れ | 5年 |
| 重加算税対象の不正 | 7年 |
ただし、以下のようなケースでは時効が中断・リセットされることがあります。
- 調査開始や督促による中断
- 延納・分納に関する同意
- 納税猶予を受けた場合
時効を過信して申告や対応を怠ると、予想外のタイミングで課税処分を受けることにもなりかねません。
まとめ

税務調査で発覚した申告漏れや納付遅れにより課される延滞税や加算税は、納税者にとって大きな金銭的負担となります。
これらの税金は、単に本税を納めれば済むものではなく、遅れた日数や申告の不備内容によって高額化するリスクがあるため、仕組みの理解と早期対応が欠かせません。
延滞税は、納期限からの経過日数に応じて税率が上がる仕組みであるため、対応の遅れがそのまま追加負担につながります。
また、加算税についても、無申告や過少申告、さらには重加算税など状況によって税率が大きく異なり、悪質と判断された場合には重いペナルティが科されます。
再発を防ぐためにも、以下の3点を意識することが大切です。
- 延滞税や加算税の計算方法を知り、自らの納税状況を把握する
- 早めの修正申告や納付によってペナルティを軽減する
- 不安や不明点がある場合には税理士に相談する
税務調査への対応や加算税・延滞税のリスクを軽減したい方には、税務調査対応に特化した税理士法人GNsのような専門家のサポートを受けることをおすすめします。経験豊富な税理士が、調査の初動対応から修正申告のサポート、今後の対策までを丁寧に支援してくれます。
正しい知識と準備で、税務調査に対する不安を安心へと変えていきましょう。