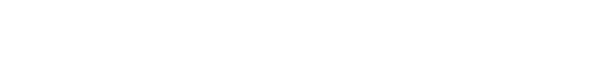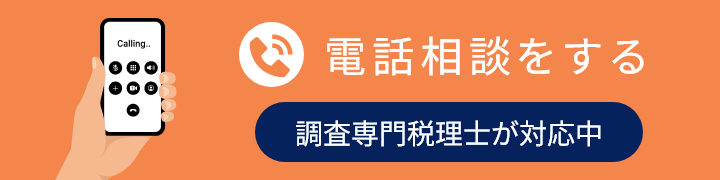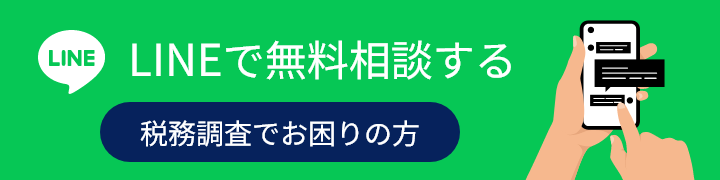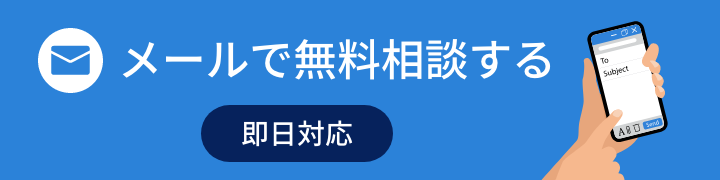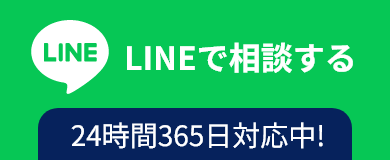目次
会社を経営していると、ある日突然国税局や税務署の調査官が訪問してくることがあります。事前通知のない「無予告調査」は、経営者や経理担当者にとって大きなストレスとなりがちです。
帳簿や資金管理に自信があっても、いざ調査官がオフィスに現れると慌ててしまうケースが多いのが実情です。
この記事では、なぜ国税局や税務署の調査が突然行われるのか、その対象となりやすい会社の特徴、調査を拒否した場合のリスク、そして実際に訪問を受けた際の正しい対応方法を詳しく解説します。
さらに、日頃からできる防衛策も紹介するので、不測の調査に直面しても冷静に行動できる知識と体制を整えることができます。
国税局の調査はなぜ突然来るのか
国税局や税務署の調査は、通常は事前に日時や場所を通知して行われます。しかし、場合によっては突然の訪問が行われることもあります。ここでは、法律的な位置づけや無予告調査が行われる背景、そして強制調査である「マルサ」との違いについて整理していきます。
原則は事前通知、例外としての無予告調査
税務調査は、調査官が持つ「質問検査権」という権限に基づいて行われます。かつては事前通知に関する明確な法律上の義務はありませんでしたが、平成23年の国税通則法改正により、調査を行う際には原則として事前に日時や場所を通知することが法律上の義務となりました(国税通則法第74条の9)。
しかし、法律は同時に例外も定めています。同法第74条の10では、事前通知を行うことでかえって正確な調査が困難になる特定のケースにおいて、通知を要しない(=無予告調査が認められる)と規定されています。
したがって、現在の法律では「事前通知が原則」ですが、合理的な理由があると税務署が判断した場合には、無予告での調査も適法に行われるのです。
無予告調査が認められる具体的な要件
国税通則法第74条の10では、事前通知を要しない具体的な理由として、事前通知をすることで正確な調査ができないおそれがある場合や、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合を挙げています。
具体的には、以下のような状況が該当します。
- ありのままの状態を調査する必要がある場合: 納税者の事業内容や過去の調査結果などから、事前通知をすると平常の事業活動が偽装されるなど、ありのままの状態を確認できなくなると判断されるケース。
- 証拠隠滅などのおそれがある場合: 事前通知をすることで、帳簿書類の隠匿や破棄、取引先との通謀による事実の隠蔽などが行われ、正確な事実の把握が困難になると合理的に推認されるケース。
マルサによる強制調査との違い
無予告調査と混同されやすいのが、国税局査察部(いわゆるマルサ)による強制調査です。両者には次のような違いがあります。
| 調査の種類 | 無予告調査 | 強制調査(マルサ) |
| 法的根拠 | 質問検査権 | 裁判所の令状 |
| 強制力の有無 | なし | あり(立入・押収) |
| 対象 | 通常の会社や個人 | 悪質な脱税容疑者 |
| 目的 | 申告内容の確認 | 刑事責任の追及 |
無予告調査はあくまで「任意調査」であり、マルサのように強制的に押収されるものではありません。ただし、拒否や不誠実な対応をすると不利になることがあります。
国税局の調査で狙われやすい会社の特徴

無予告調査は全ての会社に行われるわけではありません。国税局が突然訪問する背景には、「不正の可能性が高い」と判断される一定の特徴があります。ここでは、狙われやすい会社の代表的な傾向を整理します。
現金商売を中心にしている会社
飲食業や小売業など、現金のやり取りが多い業種は、売上の除外や計上漏れが起きやすいとみなされます。特に、国税庁が重点的に調査を行う業種として知られている、バー・クラブなどの風俗営業、美容室・エステサロン、建設業(特に一人親方)、リサイクル業、パチンコ店などは、無予告調査のリスクが高いと言えるでしょう。
現金商売では帳簿と実際の現金残高を照合しにくいため、調査官が突然訪問してレジや金庫の現金をその場で確認する「現況調査」が行われることもあります。
利益率や売上に不自然な変動がある会社
毎年の売上や利益率に大きく不自然な変動があると、意図的に数値を操作しているのではないかと疑われる可能性があります。例えば、前年に比べて売上が急減したにもかかわらず、経費が急増して赤字に転落した場合などです。
経済環境や投資など合理的な理由があれば説明可能ですが、その根拠が用意されていないと調査対象にされやすくなります。
過去に申告漏れや不正を指摘された会社
過去の調査で指摘を受けた会社は、改善状況を確認する目的で再度調査が入ることがあります。特に売上除外や架空経費が見つかっていた場合、無予告での確認が行われやすい傾向があります。
税務署の内部資料には過去の調査結果が記録されており、同じ問題が繰り返されていないかを重点的にチェックされます。
売上や資本金額が大きい会社
会社の規模が大きければ、追徴課税による徴収額も大きくなるため、資本金や売上高が一定水準以上の会社は調査対象として優先される傾向があります。特に複数の取引先や関係会社を持ち、資金の流れが複雑な会社は重点的に見られやすいです。
規模が大きくなるほど記帳や内部統制の不備が発見される確率も上がるため、狙われやすい対象となります。
突然の調査を拒否した場合のリスク
国税局や税務署からの突然の調査に対して拒否したり、その場で入室を断ることは可能です。しかし、その対応次第ではかえって疑念を招き、状況を悪化させるリスクがあります。
ここでは、突然の調査を拒否した場合に起こり得る主なリスクを解説します。
証拠隠滅を疑われる
無予告調査が行われる大きな理由は「証拠隠滅を防ぐこと」です。そのため調査を拒否すると、証拠を隠そうとしているのではないかと疑われやすくなります。
実際には単なる都合であっても、むやみに拒否した場合には調査官の視点では「何か不正がある」と見なされ、後日の調査でより厳しく追及される可能性があります。
取引先に連絡がいく場合もある
調査官が直接確認できない場合、取引先や金融機関に照会を行うことがあります。これにより、取引先に「調査を受けている会社」と知られてしまい、信用を損なうリスクが生じます。
特に取引先が大企業や金融機関の場合、継続的な取引に悪影響を与える可能性も否定できません。
国税局の無予告調査に対応する正しい流れ

突然の調査に直面しても、冷静に対応することで不利な状況を回避できます。重要なのは「慌てて不適切な行動を取らないこと」と「顧問税理士と連携して対応すること」です。
ここでは、正しい対応の流れを整理します。
まず顧問税理士に連絡する
調査官が訪問してきたら、真っ先に顧問税理士へ連絡を取ることが基本です。税理士は調査の立ち会いが可能であり、経営者や経理担当者だけでは判断が難しい場面でも適切な対応をしてくれます。
顧問税理士が同席できない状況でも、電話での助言を受けることで、その場での誤解や不利な発言を防げます。
調査官をすぐに事務所へ入れない判断基準
調査官は任意調査であれば強制的に事務所へ立ち入ることはできません。したがって、いきなり社内へ案内する必要はなく、受付や応接室で対応して構いません。
ただし、全面的に拒否すると前述のように不利になる可能性があるため、以下のような一時対応が望ましいです。
- 「顧問税理士と連絡を取りたいのでお待ちいただきたい」と伝える
- 来訪者カードや身分証を確認し、記録を残す
- 社内の書類を慌てて動かさない
このように落ち着いて対応することで、余計な疑念を招かずに済みます。
必要に応じて日程調整を申し出る方法
調査当日にどうしても対応が困難な理由がある場合は、日程変更の申し出が可能です。ただし、曖昧な理由ではなく、具体的な事情を説明することが重要です。
日程調整が認められやすい例
- 顧問税理士が不在で立ち会いできない
- 代表者が出張や入院などで不在
- 会社の決算業務や棚卸し作業などで一時的に混乱している
「本日は対応が難しいので、後日顧問税理士を交えて日程を調整させてください」と丁寧に伝えることで、調査官も合理的と判断すれば応じてくれるケースがあります。
国税局の突然の調査に備える会社の防衛策
無予告調査は、いざ訪問を受けると慌ててしまいがちですが、日頃から準備を整えておけば冷静に対応できます。ここでは、会社として備えておくべき防衛策を3つ紹介します。
帳簿や証憑を常に整理しておく
調査で最も重視されるのは、帳簿や証憑書類の正確性と整合性です。調査では、これらの帳簿や証憑書類が正しく保存されているかがチェックされます。
実務のポイント
- 売上・仕入・経費を適時に記帳する。
- 紙の領収書や請求書は日付順に整理して保管する。
- 現金出納帳と実際の現金残高が一致しているかを定期的に確認する。
社内で対応マニュアルを整備しておく
突然調査官が来たときに、誰がどのように対応するのかを明確にしておくことも大切です。マニュアルがなければ、従業員が慌てて余計なことを話してしまうリスクがあります。
マニュアルに含めるべき内容
- 調査官が来たらまず上長と顧問税理士に連絡する
- 応接室など決められた場所で対応する
- 帳簿や書類は経理責任者の承認を得てから提示する
- 不明点はその場で答えず「確認してからお伝えします」と対応する
マニュアルを共有しておけば、従業員全員が落ち着いて行動できます。
定期的に税理士とリスクチェックを行う
顧問税理士と定期的に帳簿や処理方法を確認しておくことも、防衛策の一つです。第三者の目でチェックを受けることで、思わぬミスやリスクを早期に発見できます。
特に確認しておくべき点
- 経費処理が適切かどうか
- 現金商売の管理方法
- 前回の調査で指摘された点の改善状況
- 無申告の所得や申告漏れがないか
税理士と二人三脚で管理体制を強化しておけば、調査官に対しても自信を持って説明できます。
まとめ

国税局や税務署の調査は、通常は事前通知がありますが、場合によっては突然の無予告訪問が行われます。
これは法律上認められており、特に現金商売や不自然な取引、過去の指摘がある会社は狙われやすい傾向があります。調査を拒否すれば、証拠隠滅を疑われたり、取引先に連絡が及ぶなど、かえってリスクを高めてしまうこともあります。
重要なのは、日頃からの準備と冷静な対応です。顧問税理士と連携し、調査官が来たときに慌てない体制を整えておくことで、無用なトラブルを避けられます。
帳簿や証憑を整理し、社内でマニュアルを共有し、定期的に税理士とリスクチェックを行うことが最大の防衛策です。
突然の訪問は決して珍しいことではありません。だからこそ、事前の備えと正しい知識で対応し、会社の信用と経営の安定を守ることが大切です。
税理士をお探しなら、税理士法人GNsへご相談ください。突然の税務調査や無予告調査に対して豊富な対応実績を持つ税理士法人です。
企業の立場に立ち、次のようなサポートを提供しています。
- 突然の調査訪問時の初動対応アドバイスと立会い
- 調査官との交渉・日程調整のサポート
- 帳簿や証憑のチェック体制の強化支援
- 再発防止のためのリスク診断と改善提案
無予告調査は、準備不足の会社ほど動揺しやすく、誤った対応が大きな不利益を招きかねません。税務調査に特化した専門家がそばにいることで、調査時の負担を大幅に軽減し、経営に集中できる環境を守ることができます。