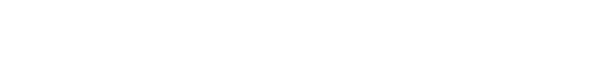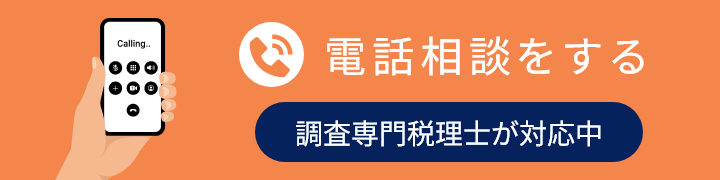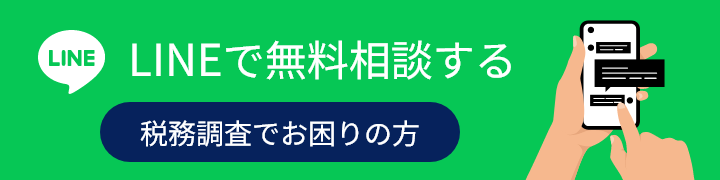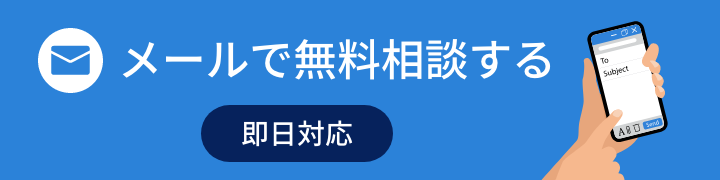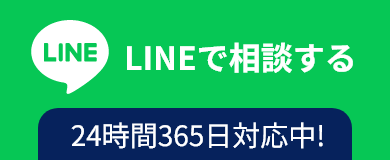目次
税務調査の通知を受けると、多くの事業者がまず気にするのが「何年分さかのぼられるのか?」という点です。
通常、税務調査は3年から5年が対象とされていますが、一定の条件下では7年に遡って調査が行われることがあります。この「7年遡及」の根拠や対象となるケースを正しく理解し、適切に対応することが重要です。
この記事では、国税通則法に基づいた7年遡及のルールを詳しく解説しつつ、実際に7年遡及されたケースやリスク、さらに帳簿保存の注意点や対策方法まで幅広く取り上げていきます。
不安を抱える経営者や個人事業主の方が、適切な準備と対応ができるようになることを目指します。
税務調査の遡及期間とその根拠を理解しよう
税務調査では通常、直近3年または5年が調査対象期間とされますが、すべてのケースでそうとは限りません。法律上の根拠や調査官の判断により、最大で7年まで遡ることが可能です。
ここでは、一般的な遡及期間と7年遡及の法的根拠、不正と見なされる行為の影響について解説します。
法律上の遡及期間は5年間
税務調査で遡って調査できる期間は、法律(国税通則法)上、原則として申告期限から5年間と定められています。
ただし、実務上の運用では、まず直近3年分を対象に調査が開始されることが多いため、「調査は3年分」というイメージが広く持たれています。しかし、これはあくまで実務上の慣行です。調査の過程で申告漏れなどの誤りが発見された場合、法律の規定に基づき、調査範囲が5年間に拡大されることは一般的です。
- 法律上の原則(5年): 税務署が更正(追徴課税)を行える期間。申告に誤りがあれば、この期間まで遡って調査が行われる。
- 実務上の調査期間(3年~): 調査の起点となる期間。特に問題がなければこの範囲で終わることもあるが、あくまでスタート地点と考えるべき。
「最初は3年分と言われたのに5年分に延長された」というケースは、法律上、当然に起こりうることなのです。
国税通則法第70条に基づく7年遡及の根拠
7年まで遡及できる根拠は、国税通則法第70条にあります。この条文では、以下のように定められています。
「偽りその他不正の行為により税額を免れ、または還付を受けた場合には、7年の遡及が可能」(国税通則法第70条より)
つまり、単なるミスやうっかりではなく、故意的な不正行為があったと税務署が判断した場合に限り、7年までさかのぼって税務調査が行われるのです。
無申告や偽りその他不正の行為があった場合
国税通則法でいう「偽りその他不正の行為」には、次のような行為などが該当します。
- 売上の隠蔽
- 架空経費の計上
- 二重帳簿の作成
- 帳簿書類への虚偽記載
これらの行為があると税務署に判断された場合、7年遡及だけでなく、重加算税といった厳しいペナルティも発生する可能性が高いです。
これは、偽りその他不正の行為は厳密には「ほ脱の意図をもって、その手段として税の賦課徴収を不能又は著しく困難ならしめるような何らかの偽計その他の工作を行うこと(昭和42.11.8最高判決)」をいい、重加算税の要件である「仮装・隠蔽行為」と似たような意味を持ちます。
根拠となる条文は異なるものの、実際の調査の現場では、重加算税と7年遡及の根拠はほぼ同義であると考えられることが多いためです。
「うちは大丈夫」と思っていても、税務調査の対応に不備があると些細な処理ミスが「不正」と見なされてしまう可能性もあるため、過去の処理について心配な点があれば、専門家に相談することが重要です。
税務調査で7年遡及される具体的なケース
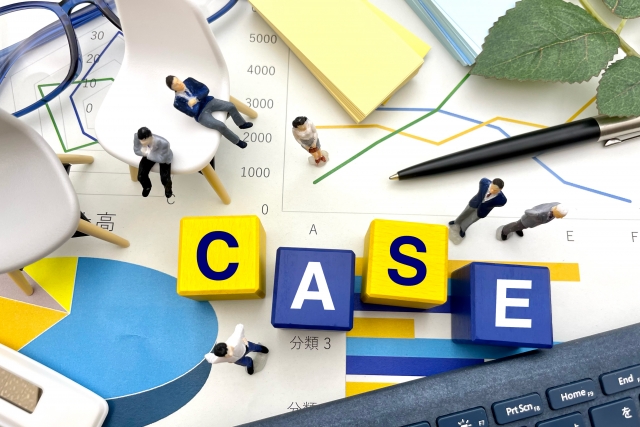
7年遡及はすべての事業者に適用されるわけではありません。しかし、不正を働いていると判断された場合、7年分さかのぼって調査が行われることがあります。
ここでは、実際に7年遡及の対象となる具体的なケースを紹介し、どのような行為が「不正」と見なされるのかを解説します。
無申告が続いている場合
確定申告をまったくしていない「無申告」の状態が複数年にわたって続いている場合、税務署はそれを厳しく追及します。
無申告が続くと以下のようなリスクが発生します。
- 税逃れのために意図的に無申告を継続したと判断されるおそれがある
- 国税通則法第70条により7年遡及のリスク
- 重加算税の適用対象になる可能性が高まる
例えば、フリーランスで開業届を提出したにもかかわらず数年間申告をしていない場合、その間の収入を税務署が把握した時点で過去7年分の申告義務が問われ、追徴課税を受けるリスクが高まります。
なお、無申告が継続している場合、当初から5年分は遡って調査されることはほぼ確実です。
仮装や隠蔽など不正と見なされる行為がある場合
税務調査では、単なる記帳ミスではなく、「仮装」や「隠蔽」といった意図的な不正行為があるかどうかもチェックされます。
不正とされる代表的な例は以下の通りです。
- 売上を一部除外して記帳
- 架空の外注費や給料を計上
- 経費を水増し
- 二重帳簿の作成
これらの行為は、「偽りその他不正の行為」とされ、7年の遡及調査に加え、重加算税(最大50%)の課税対象にもなります。税務署側が不正の証拠を掴んだ場合は、調査が厳格に行われるため注意が必要です。
重加算税が適用されるケース
重加算税とは、悪質な脱税行為に対して課される追加の税金です。通常の過少申告加算税などとは異なり、非常に重い負担となることが特徴です。
重加算税のポイントは以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
| 税率 | 過少申告の場合:原則35% 無申告の場合:原則40% |
| 適用条件 | 仮装・隠蔽などの「不正行為」があった場合 |
例えば、故意に売上を抜いた場合や、調査に際して虚偽の説明を行った場合は、重加算税が適用され、さらに7年分にわたって追徴される可能性が極めて高くなります。
7年遡及されたときに発生するリスク
税務調査で7年遡及が適用された場合、調査対象期間が長くなるだけでなく、高額な追徴課税や精神的・経済的な負担が一気に増加します。ここでは、7年遡及によって生じる主なリスクについて具体的に説明していきます。
重加算税や延滞税による追徴課税
7年遡及が適用されると、追徴税額は膨大になります。さらにそこに重加算税や延滞税が加算されることで、支払総額は想像以上に膨らみます。
- 重加算税は、過少申告で35%、無申告で40%と極めて高い税率が課される
- 延滞税は、単なる過少申告であれば1年で延滞計算がストップするところ、重加算税が適用された場合は納期限の翌日から納付日まで発生するため、長期化するほど多額の負担となる
例えば、500万円の不正による追徴税額があった場合、35%の重加算税と延滞税が課されると、追加で200万円以上の納税義務が生じるケースもあります。支払えない場合には、差押えなどのリスクもあるため、事前の対応が重要です。
調査期間が延びることによる多額の追徴課税リスク
税務調査では、当初3年または5年と通知されていたとしても、調査の過程で不正が発見されると、調査期間が最大7年に延びることがあります。
調査期間が延びることで起こる問題
- 調査対象年数が増えることで、追徴課税の金額が大きく膨らむ
- 書類が残っていない期間に遡及されると、推定課税により不利な計算がされることがある
- 申告や帳簿に誤りがある年が多ければ多いほど、合計の税額・罰則が増える
たとえば、当初3年分の調査と想定していたのに、不正行為が発覚して7年に延長された場合、追徴税額が2倍以上になる可能性も大いにあります。さらに、過去の資料が揃っていなければ、納得のいかない金額を課されることもあり、精神的なダメージも大きくなります。
こうしたリスクを避けるためには、最初から正確な帳簿と誠実な申告が不可欠です。不安があれば、調査前に専門家に確認してもらうことが重要です。
税務調査の頻度が上がる可能性
調査中に不正が判明した場合、今後、重点的に調査の対象となり、調査頻度が上がる可能性があります。特に法人の場合は税務調査のサイクルが狭まるともいわれています。
帳簿や書類の保存期間と調査対象の関係

税務調査で過去を遡られる際、まず調査官がチェックするのは帳簿や証憑書類です。保存期間を過ぎた書類であっても、状況によっては調査の対象になり得ることがあります。
ここでは、法人・個人事業主それぞれに求められる保存期間と、保存期間を過ぎた書類に対する税務署の対応について解説します。
法人に求められる帳簿や書類の保存期間
法人の場合、税法や会社法で帳簿書類の保存期間が定められており、税務調査に備えて確実に保管しておく必要があります。
法人の帳簿書類の保存期間は、原則として7年間です。
ただし、例外として、青色申告法人で欠損金(赤字)が生じた事業年度においては、その帳簿書類を10年間保存しなければなりません。これは、欠損金を将来の黒字と相殺(繰越控除)できる期間が10年間であるためです。
したがって、すべての青色申告法人に一律で10年の保存義務があるわけではなく、「原則7年、ただし欠損金が発生した場合は10年」と理解するのが正確です。自社の申告状況に合わせて、必要な期間、書類を保管することが重要です。
個人事業主に求められる帳簿や書類の保存期間
個人事業主にも、所得税法により帳簿や書類の保存が義務付けられています。保存期間は青色申告か白色申告か、また書類の種類によって異なり、主に5年または7年と定められています。
特に、白色申告でも7年間保存が必要な帳簿があるなど、誤解しやすい点も多いため、以下の表で正確に確認しておきましょう。
【個人事業主における主な帳簿・書類の保存期間】
| 書類の種類 | 青色申告 | 白色申告 |
| 帳簿類(仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳など) | 7年 | 7年 |
| 決算関係書類(損益計算書、貸借対照表など) | 7年 | ― ¹ |
| 現金預金取引等関係書類(領収書、預金通帳など) | 7年 ² | 5年 |
| その他の書類(請求書、見積書、契約書など) | 5年 | 5年 |
¹ 白色申告には、貸借対照表などの決算書の作成義務はありません。
² 青色申告の方でも、前々年分の事業所得および不動産所得の金額が300万円以下の場合、現金預金取引等関係書類(領収書、預金通帳など)の保存期間は5年となります。
保存期間を過ぎた書類が調査で問われる場合
保存期間が経過していても、税務調査の対象から完全に除外されるわけではありません。とくに不正行為が疑われる場合や、調査が7年に遡及された場合には、過去の取引内容の確認を求められることもあります。
法定の保存期間内に帳簿や証憑がすでに廃棄されていた場合、「なぜ残していないのか?」という疑問から、調査官の心証が悪くなる恐れもあるため、可能な限り保管しておくことが得策です。
なお、消費税の納税義務は基本的に2年前(2期前)の売上などをもとに判定するため、税務調査においても、5年前の年分の消費税判定のために、7年前の売上明細や口座履歴を確認されることはありますので留意してください。
税務調査で7年遡及を避けるためにできること

7年遡及の対象となるのは、「偽りその他不正の行為」があると判断されたケースに限られます。つまり、日頃からの正しい会計処理や申告、税理士との連携ができていれば、7年遡及のリスクは大幅に低減できます。ここでは、調査で不正と見なされないための実践的な対策を紹介します。
日頃から帳簿や書類を正しく整理しておく
基本中の基本ですが、帳簿・証憑書類の整備状況が税務署からの信頼を得るうえで最も重要なポイントです。次のような点を日頃から意識することで、不正と疑われるリスクを防げます。
正しく整理するためのポイント
- 取引ごとに証憑(請求書、領収書、契約書など)を保存
- 定期的な帳簿記帳や現金・棚卸在庫などの照合の実施
- 試算表や決算書のチェック体制の整備
日常的に帳簿と実態が一致している状態を維持していれば、調査官に「不正がない」印象を与えることができ、調査の短縮や対象期間の軽減にもつながります。
無申告や曖昧な処理を避ける
申告そのものを怠ったり、明らかに説明がつかない処理をしていると、それだけで不信感を持たれます。以下の点は特に注意が必要です。
注意すべき処理
- 売上の計上漏れ(入金だけで未計上)
- 経費の水増し
- 年間通して申告を放置する無申告
- 実体のない外注費や交際費
こうした処理があると、「偽りその他不正の行為」とされやすく、7年遡及や重加算税の適用が現実味を帯びます。曖昧な点があれば、必ず専門家に確認を取りましょう。
特に無申告には税務署も厳しく対応するため、税務調査が来る前に早期に申告を済ませることが大切です。
税理士と連携しリスクを早めに点検する
最も効果的な対策の一つは、信頼できる税理士と定期的に相談する体制を整えることです。特に次のような点を重点的にチェックしてもらうと安心です。
- 経理処理のルールや記帳方法が適切か
- 過去の申告内容に不備がないか
- 税務調査時の想定リスクと対応方法
税理士をお探しなら税理士法人GNsにご相談ください。税務調査に特化した税理士が数多く在籍しています。
- 税務調査に特化した税理士による徹底サポート
- 調査対応実績が豊富
- 企業ごとのリスク診断や、事前相談にも柔軟に対応
「うちは大丈夫かな?」と少しでも不安を感じている方は、調査が入る前に相談することで、無用なリスクや損失を回避できる可能性が高まります。
まとめ
税務調査において「7年遡及される」というのは、誰にとっても大きな不安材料です。しかし、その根拠や対象となる条件は法律で明確に定められており、不正がない限り7年まで遡られることはありません。
国税通則法第70条に基づき、偽りや隠蔽などの行為が確認された場合にのみ、通常の3年または5年から7年に調査期間が延びることになります。
最も重要なのは、日常的な帳簿整理と適正な申告を行うことです。無申告や不適切な処理があると、重加算税や延滞税といった多額の追徴課税につながる可能性があります。また、調査に備えて帳簿や書類の保存期間をしっかり守ることも大切です。不安がある方や、「もしかして対象になるかも」と感じる方は、早い段階で税理士法人GNsのような税務調査に強い税理士に相談することで、無用なリスクを避けることができます。信頼できるパートナーとともに、安心して事業を継続できる体制を整えていきましょう。