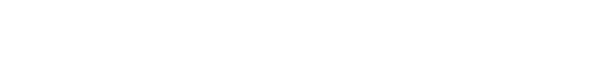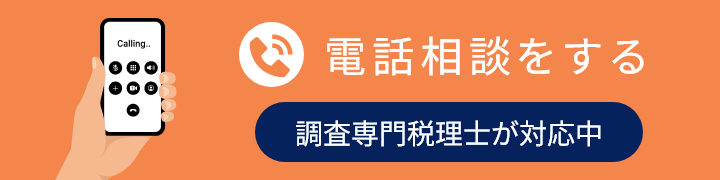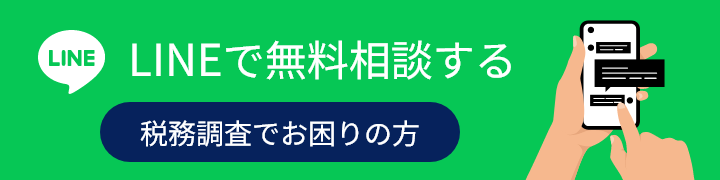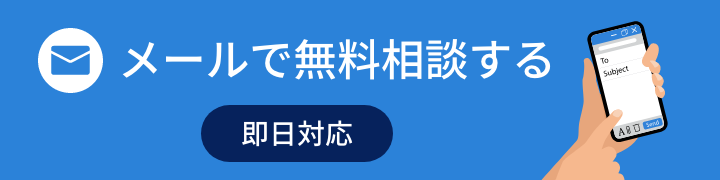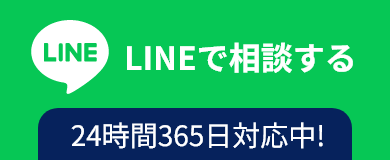目次
税務調査を受ける際、「領収書が見つからない」「うっかり破棄してしまった」といった状況に直面することがあります。特に個人事業主や中小企業の経営者にとって、領収書の有無は経費認定の大きなカギを握っているため、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、領収書がない場合のリスクや、代替手段で経費として認められるための具体的な方法を解説します。
さらに、消費税やインボイス制度に関連する注意点や、書類管理の実践的なポイントも網羅。調査を控えている方が、落ち着いて対応できるような知識と対策が得られるようになります。
税務調査で領収書が確認される理由
税務調査において、領収書は重視される証憑資料の一つです。調査官は、申告内容と支出の整合性を確認するために領収書をチェックします。ここでは、調査で確認される書類の種類や、なぜ領収書が経費の根拠として重要視されるのかを解説します。
税務調査の目的と確認される主な書類
税務調査の主な目的は、適正な申告がなされているかどうかの確認です。そのために以下のような書類が調査対象になります。
調査で確認される主な書類
- 領収書、請求書、納品書などの支出証明
- 帳簿(現金出納帳、売掛帳、経費帳など)
- 通帳・クレジットカード明細
- 契約書や注文書
- インボイスまたは適格請求書
とくに支出関連の領収書は、「いつ・何に・いくら使ったのか」を確認するための一次証拠として位置付けられており、領収書の有無で経費の認否が大きく左右されることがあります。
領収書が経費の根拠として重要視される背景
領収書は、支出の事実性・金額・取引相手の情報をまとめて証明できる書類です。そのため、税務署は「正当な経費」であるかどうかを判断するうえで、領収書を重視します。
領収書が重視される理由
- 支出の発生日・金額・相手先が明記されている
- 改ざん・捏造が難しく、信憑性が高い
- 消費税額が記載されていることも多く、仕入税額控除の裏付けになる
特に近年はインボイス制度の導入により、消費税の控除対象として適格請求書や領収書の提出が求められる傾向が強まっており、領収書の重要度はますます高まっています。
保存期間と調査で着目されやすいポイント
税法上の帳簿や書類の保存期間は、法人と個人事業主で異なります。
法人の場合:帳簿および書類の保存期間は原則として7年間です。ただし、赤字決算(繰越欠損金)が生じた事業年度の書類は10年間の保存が義務付けられています。
個人事業主の場合:主な帳簿・書類の保存期間は以下の通りです。
| 書類の種類 | 青色申告 | 白色申告 |
| 帳簿類(仕訳帳、総勘定元帳など) | 7年 | 7年 |
| 決算関係書類(損益計算書、貸借対照表など) | 7年 | ― ¹ |
| 現金預金取引等関係書類(領収書、預金通帳など) | 7年 ² | 5年 |
| その他の書類(請求書、見積書、契約書など) | 5年 | 5年 |
¹ 白色申告には、貸借対照表などの決算書の作成義務はありません。
² 青色申告の方でも、前々年分の事業所得および不動産所得の金額が300万円以下の場合、現金預金取引等関係書類(領収書、預金通帳など)の保存期間は5年となります
税務調査では、申告書の内容と照らし合わせて、これらの保存された書類との整合性を確認されます。
調査で着目されるポイント
- 領収書の金額や日付が帳簿と一致しているか
- 自社事業と無関係な支出が経費に含まれていないか
- 領収書の保存状態(紛失・破損・不鮮明など)
保存が不十分であったり、説明が曖昧な場合には、経費否認や推計課税に発展するリスクが高くなります。調査に備えて、書類の保管・整理を定期的に見直すことが大切です。
領収書がない場合に経費否認されるリスク

税務調査で領収書が提示できない場合、経費として認められない可能性があるだけでなく、追徴課税や加算税の対象となるリスクもあります。ここでは、領収書なしによる経費否認や、推計課税、さらに消費税への影響について解説します。
経費否認や推計課税が適用される可能性
税務調査で領収書や請求書がないと、調査官はその支出の信ぴょう性を疑い、経費として認めない判断(経費否認)を下すことがあります。それにより、課税所得が増え、税額が増加することになります。
さらに、帳簿や証憑が整っていない場合、税務署が所得金額を推定する「推計課税」を行う可能性もあります。推計課税は一定の割合を用いて経費額などを推計する方法です。これが適用されると、以下のようなデメリットが生じます。
- 実際よりも高い所得と見なされ、税額が増加する可能性がある
- 消費税の仕入税額控除が適用されないリスク
- 調査が長引く可能性
たとえば、外注費や仕入れ費用が証明できなければ、架空の費用ではないかと疑われて実態と乖離した納税義務を負うことになりかねません。
重加算税や延滞税が課されるケース
領収書がないだけでなく、「仮装や隠蔽」といった意図的な不正行為があったと判断された場合、通常の加算税よりはるかに重い「重加算税」が課されます。この税率は、不正の内容(過少申告か無申告か)によって異なります。
重加算税・延滞税のリスク
| 税目 | 内容 |
| 重加算税 | 不正の内容に応じて、以下の税率が適用されます。 ・過少申告の場合:追加で納める税額の35% ・無申告の場合:納付すべき税額の40% |
| 延滞税 | 納期限の翌日から日数に応じて発生する利息的な税 |
「故意に経費を過大に申告した」「経費の証明がまったくできない」「領収書類を故意に破棄した」などの事例では、重加算税の対象となるリスクが生じます。
消費税の仕入税額控除に影響するリスク
消費税の申告においては、仕入税額控除(支払った消費税分を控除できる制度)を適用するために、「帳簿及び請求書等の保存」が必須です。
領収書がない場合に起こる問題
- 適格請求書(インボイス)ではない領収書類の場合、一部が控除対象外になる
- 領収書や請求書の保存がない場合、法人税や所得税上の経費としては認められても、消費税の仕入税額控除ができない
インボイス制度導入後は、消費税の控除要件が厳格化されており、領収書がないことで大きな損失につながる可能性があります。
特に法人税や所得税上の「経費」と消費税の「仕入税額控除」の定義は異なり、消費税の「仕入税額控除」は領収書等の保存がない場合には否認されている事例が数多くあるため、注意が必要です。
税務調査で領収書がなくても経費が認められるケース
領収書が手元にない場合でも、他の客観的な証拠により「支出の事実」を立証できれば、経費として認められる可能性があります。ここでは、実際に認められた例や、代替書類の活用方法について具体的に解説します。
クレジットカード明細や通帳記録で支出を証明できる場合
領収書がない場合でも、クレジットカード明細や銀行通帳の記録から支出の事実を証明できることがあります。特に、金額や日付が正確に記録されていることが評価されます。
証明力のあるデータ
- クレジットカード利用明細(発行元の正式なもの)
- 銀行口座の取引履歴(ネットバンキングの画面コピーも可)
- それらと一致する帳簿記録
例えば、出張で宿泊したホテルの領収書を紛失してしまった場合でも、カード明細に「支出先・金額・日付」が記載されていれば、経費として認められることがあります。
ただし、現金支払いの場合は証明が困難になるため、カードや振込など記録に残る手段で支払う習慣を持つことが重要です。
請求書や納品書など代替書類がある場合
取引先からの納品書や契約書といった他の証憑類がある場合も、領収書に代わる証拠として経費認定されることがあります。
代替として有効な書類
- 納品書(相手先・日付・金額・内容が記載されているもの)
- 発注書・注文書・業務委託契約書
- メールの送受信記録やチャット履歴(取引の流れを証明)
たとえば、フリーランスの業務委託費に関して、契約書・振込明細がセットで揃っていれば、領収書がなくても問題視されないことが多いです。
重要なのは、支出の内容・金額と発生の時期、取引相手が誰であるかを他の資料から確認できることです。
日付や金額を記載した出金伝票を活用する場合
現金で支払った場合に領収書を紛失してしまった場合は、出金伝票を活用することも一つの方法です。これは、支払者自ら作成する帳票であり、正確に記載されていれば証拠として一定の評価を受けます。
出金伝票のポイント
- 支出日、支払先、金額、用途を明確に記載
- 社判や担当者の署名を添える
- 他の証憑(会話履歴・業務報告など)と一緒に提出
ただし、出金伝票は第三者が発行した証憑ではないため、信憑性はやや劣ります。できる限り他の資料と併せて提出し、合理的な説明ができる状態を整えておくことが大切です。
領収書を紛失した場合の具体的な対応方法
領収書をうっかり紛失してしまった場合でも、正しい対応を取ることで経費として認められる可能性は十分にあります。ここでは、実際に取れる対応策を具体的に紹介します。調査前に準備しておくことで、リスクを最小限に抑えられます。
取引先に領収書の再発行を依頼する
領収書を紛失した場合、まず最初に取引先へ再発行をお願いするのが基本です。多くの企業や店舗では、過去の取引記録が残っていれば再発行に応じてくれることがあります。
再発行依頼のポイント
- 取引日・金額・支払方法を明確に伝える
- 支払いに使用した証憑(明細書や通帳記録)があるとスムーズ
- 電話やメールで記録が残る形で依頼する
ただし、法律上は「領収書の再発行義務」はありません。そのため、どうしても再発行が難しい場合は、他の証拠資料の準備が必要です。
クレジットカードやレシートで支出を裏付ける
再発行が難しい場合でも、クレジットカードの明細や、口座からの支払履歴があれば支出を裏付けられるケースが多いです。なお、レシートも立派な証拠となるため、日常的に保管しておく習慣が重要です。
証拠として使える資料
- クレジットカード明細(店名・日付・金額が記載されていること)
- レシート(可能であれば支出内容が明記されているもの)
- 領収書がない旨の社内メモや説明資料
特に最近では、電子レシートやアプリでの履歴など、デジタル証拠も有効な手段となります。スマホ決済やクラウド会計ソフトなども活用すると、証拠集めがよりスムーズになります。
推計課税を避けるために代替資料を準備する
領収書が出せない場合でも、他の資料を組み合わせて支出の実態を説明できれば、税務署側が納得する可能性は高くなります。これにより、推計課税や経費否認を防ぐことができます。
代替資料として有効なもの
- 支出の目的を記録したメモや報告書
- 業務に関する会話の記録(メール・チャット)
- 業務日報やスケジュール帳などの行動記録
ポイントは、「その支出が本当に存在して事業に必要だったのか」を、総合的な資料で証明することです。1つの資料だけでは不十分でも、複数の要素を組み合わせることで、税務署側も判断材料を得やすくなります。
インボイス制度や電子帳簿保存法への対応
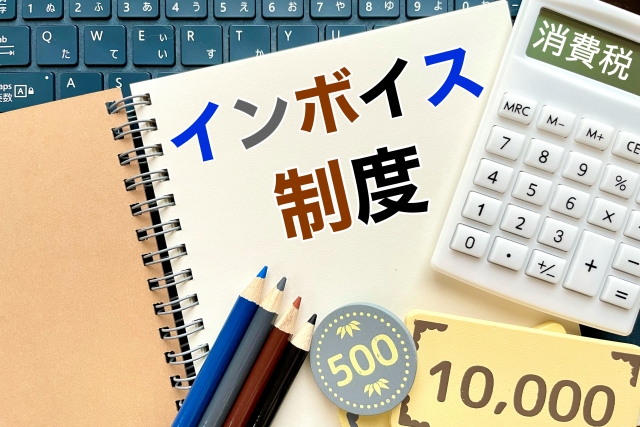
2023年10月に開始されたインボイス制度や、強化される電子帳簿保存法により、経費処理や証憑管理に求められるレベルが以前よりも厳しくなっています。
領収書がない場合の対応だけでなく、制度変更に合わせた準備が必要です。ここでは、制度ごとのポイントを解説します。
インボイスがないと仕入税額控除ができない理由
インボイス制度では、「適格請求書発行事業者」が発行するインボイス(適格請求書)でなければ、消費税の仕入税額控除を全額受けることができません。そのため、インボイスがない取引では、実際に支出があったとしても控除が全額認められないリスクがあります。
インボイスなしで控除できない理由
- 発行者の登録番号が確認できない
- 消費税額が明記されていない
- インボイス登録事業者からの仕入であることを証明できない
このように、消費税の申告ではインボイスの保存が法的義務となっており、領収書がインボイスでない場合は、たとえ経費として認められても消費税控除は全額できません。
少額特例が適用される場合
インボイス制度には、少額取引(1万円未満)に関しては一定の帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる緩和措置が設けられています。これにより、小規模な支出に対しては、一定の条件下で控除が認められる場合があります。
少額特例の概要(2029年9月30日までの経過措置)
- 1万円未満の支出については、インボイスがなくても仕入税額控除が可能
- 帳簿に必要事項を正確に記載することが条件
- 領収書の提出が求められる可能性もあるため、保管は推奨
ただし、この特例はあくまで一時的な措置であり、一定規模以下の事業者に認められた制度です。2029年以降は1万円未満の取引でもインボイスの保存が必要となるため、今のうちから対応の準備を進めておくことが必要です。
電子帳簿保存法と証憑管理の関係
電子帳簿保存法では、紙の帳簿や書類をスキャンしてデジタルデータとして保存する(スキャナ保存)ことが認められています。ただし、保存要件は年々厳格化されています。
電子保存の主な要件
- 真実性の確保(タイムスタンプ、改ざん防止措置)
- 可視性の確保(検索性・見読性)
- 関連書類との紐付け管理
これにより、紙の領収書を廃棄しても、正しく電子化されていれば証拠書類として認められます。クラウド会計ソフトやスキャナアプリを活用し、証憑管理のデジタル化を進めることが、今後の調査対応に有利になります。
ただし、実際のスキャナ保存の要件は非常に細かく設定されているため、対応する際には、税理士に相談することやスキャナ保存に対応したアプリを利用することが大切です。
税務調査に備えた日常的な書類管理のコツ
領収書を紛失したり、証拠書類が不完全な状態は、税務調査時に大きなリスクとなります。そのリスクを防ぐためには、日々の書類整理や記録の取り方に意識を向けることが重要です。ここでは、調査に備えて安心できる状態をつくるための実践的な管理方法をご紹介します。
領収書や明細を整理して定期的に点検する
領収書や明細は、「溜めずにすぐに整理・分類」することがポイントです。月に一度など、定期的な見直しを行うことで、紛失や混乱を防げます。
書類整理のコツ
- 日付順・取引先別にファイリング
- 紙の領収書はスキャンしてクラウドに保存
- クラウド会計ソフトに明細や証憑をひもづけておく
- 破損・退色の恐れがあるレシートは早めに保存処理
また、スマートフォンのアプリを使えば、外出先でもすぐにデジタル保存が可能です。こうした習慣づけにより、調査時に慌てるリスクを大きく減らせます。
個人用と事業用の支出を分けて記録する
事業をしていると、プライベートと業務の支出が混在しがちです。この区分が不明確だと、調査官から不信感を持たれ、経費否認につながるリスクが高まります。
区分管理の方法
- 事業用口座・クレジットカードを別に用意する
- 帳簿に内容を明確に記録
- 曖昧な支出は備考欄に利用目的を記載する
事業用の支出だけを整理しておくことで、帳簿全体の信頼性も高まります。また、個人事業主にとっては確定申告時の作業もスムーズになるメリットがあります。
不安な場合は税理士に相談して早めに対策する
領収書の扱いや経費の妥当性について、自分だけで判断するのは難しいこともあります。少しでも不安がある場合は、税理士に相談することが最も確実な対策です。
税理士に相談すべきタイミング
- 大口の支出で証憑が不完全な場合
- 経費処理に自信がない取引がある場合
- 税務調査の通知を受けた・入りそうな気配がある場合
税務調査対応に強い税理士法人GNsでは、領収書がないケースでも適切なアドバイスと書類整備の支援を提供しています。
GNsが選ばれる理由
- 税務調査の経験豊富な税理士が在籍
- 税務調査時の書類不備を予防するためのアドバイス
- クラウド会計との連携・デジタル化にも対応
「この経費、通るかどうか不安…」と感じたら、事前にプロに相談し、万全な備えを整えることで、調査時の精神的な負担も大幅に軽減されます。
まとめ

税務調査において、領収書がない状態は経費否認や追徴課税といったリスクを招く要因となります。しかし、領収書がなくても、クレジットカード明細や口座の出金履歴、出金伝票といった代替資料で支出の実態を適切に証明できれば、経費として認められる可能性があります。
特に、推計課税や重加算税といった厳しい処分を避けるには、日常から証憑管理を徹底することが重要です。インボイス制度や電子帳簿保存法の対応も求められる現在では、紙の保管だけでなく、デジタルでの整備や運用も欠かせません。
不安を感じた際には、税務調査に強い税理士法人GNsのような専門家に早めに相談することで、的確な対策と安心感を得ることができます。正しい書類管理と準備で、調査にも自信を持って対応できる状態をつくっていきましょう。